こんにちは。横浜・鎌倉のプロ家庭教師 佐々木(@kateikyo_megumi)です。
話が「わかる」「わからない」、あの人の話は「わかりやすい」「わかりにくい」といいますよね。
勉強を教わるなら、断然「わかりやすい」人から教わりたいはずですし、お子さんの勉強は「わかりやすく」説明できる人に見てもらいたいと思うでしょう。
でも、「人に説明するの苦手なの~!!!」と、説明することに苦手意識を持っている人も多いと思います。正直私もそうです。だって私口下手だし、シャイだし…。
ですが、口下手シャイおばけ(?)の私でも、理論武装しつつアレコレ練習しているうちに、「説明わかりやすかったです」と言っていただけるようになりました。わーい\(^o^)/
そこで今日は、口下手でもできる「わかりやすい説明をするコツ」について書いてみようと思います!
私より口下手な人は人はそうそういないでしょうから、これをやっていただければ大丈夫!
わかりやすい説明のコツ① 準備する

わかりやすい説明は準備が肝心
準備が大事
口下手な人や説明に自信がない人なら分かると思うんですけど…人に説明するときって怖いですよね?手が震えますよね?
うまくいかなかったらどうしよう?
ポカーンとされたらどうしよう?
わからないことを聞かれたらどうしよう?
なんてことを考えてしまいますよね。
恐ろしいことにならないために大切なのは、準備をすること!かならず話す内容を先に考えておきましょう!
書き出す
説明で話したいことを考えて、いちどすべて書き出します。
これは実はすごく大事なことなんです。説明内容に過不足があると、口下手な人は慌ててしまうんですよね。なんでわかるかって?それは私が口下手だからさ!!
突然パニックにならないためにも、ネタをしっかり出して、安心してしゃべりましょう。
それに、書き出していると、関連事項が思い浮かんできてネタが出てきたりしますし、書いていると頭がスッキリしてくる効果もあります。
書くときは、ふせんやメモなど、小さな紙に書くのがおすすめ。教えながら「あわわわわわ」とならないように、ネタを出し尽くしましょう。
わかりやすい説明のコツ② 分ける

わかりやすいとは「分ける」こと
わかるとは「分ける」こと
わかりやすい説明とはそもそも何なのかというと、「分けられている説明」だと私は答えます。
わかるは「分かる」と書きますね。つまり、分かるようにするとは、分離したり、グループ分けすること、と私は解釈しています。違いを明確にしたり、基準を明確にすること、ともいえますね。
わかりやすく話すとか、わかりやすさを得るためには、何らかの基準をもって、分けることがポイントになります。
基準のつけ方はたくさんあります。
・基本的なことと、応用的なこと
相手に合わせて話をする際は、
・相手が実践できていることと、できていないこと。
・相手が得意なことと、そうでないこと。
・相手に今必要なことと、すぐに必要ではないこと。
このように分けることもできますね。
さきほど話すことをざっと書き出しているはずですから、それをグルーピングしましょう。ふせんなら分けたり順番に並べたりしやすいのでおすすめですよ!
頭のなかはクローゼット
人間の頭の中はごちゃごちゃしています。例えるなら、人間の頭の中は、ぐちゃぐちゃなクローゼットのようなもの。
クローゼットに、たたまずに洋服をドサッと入れているような状態です。このままでは次に使う時に必要なものを見つけることができません。
そこですべきことは、基準をもって分けて保管することです。
例えば、シャツとスカートという機能別に分けるのもいいでしょう。
点数が多いなら、さらに同じ色のものをそろえて色別に分けるとスッキリ。次の時も使いやすいですね。
わからない状態というのは、基準がなく、「とりあえず入れてみた」状態だと思ってください。
だからぐっちゃぐちゃで、混乱するのです。
わからない状態とは、これらが混ざってぐちゃぐちゃだから、「訳がわからない」状態に陥るのです。
わかりやすい教え方のコツ
人に教えるときには、教える内容に対して、最適な基準をもって分けていくことがポイントです。
つまり「できていること」と「できていないこと」や「できるようになりたいこと」と「別に重視しないこと」が分けられていることがとても重要なのです。
自分で勉強するときも同じです。どこまでは理解できて、どこは理解できていないのか。
自分の課題は何なのか。
それらを分けてみることから始めてみてはいかがでしょうか(^^)/
わかりやすい説明のコツ③ 構成する

わかりやすい説明の構成法
わかりやすく伝える構成法があります。この順番に言えば伝わるというパターンですね。
その中で有名なのは、PREP法です。
要点を伝えるPREP法
要点をわかりやすく伝えるテンプレートとして、PREP法があります。
Point(要点)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(要点)の頭文字ですね。この順番で話すと伝わりやすいです。
人に説明するときは、準備が大切です。
なぜなら、準備をしないと内容が飛んでしまったり、余計なことを話してしまうからです。
学生の頃、話がどんどん脱線していく先生はいませんでしたか?話し手が混乱していたり、変な方向に話が向いていくと、聞いている私達まで頭が混乱しますよね。あなたにもそんな経験、ありませんでしたか?
だから人に説明するときには、ぜひ準備をしてくださいね。
こんなふうに、要点を述べ、その理由や具体例を述べる方法です。
「今回の要点はこれです。その理由は○○だからです。例を上げましょう、△△の時には」
何かを教えたり、プレゼンするときに使えそうです。
このテンプレは他にも説得力のある主張をするためのAREA法、結論を伝えるCREC法もあります。
詳しくはこちらの記事をぜひ。

わかりやすい説明のコツ④ 図を使う

図を使うと4倍伝わる
しゃべりに自信がない人にこそおすすめしたいのが、「図を使う」という方法です。
絵や図を上手に使えば、伝わりやすいだけでなく、しゃべることも少なくて済みますしね!一石二鳥すぎる!!
なぜ、「ちゃんと」は伝わらないのか?
ちょっと専門的なお話を。
カナダの心理学者ペイヴィオは、
・具体語(ピアノなど)
・抽象語(正義など)
の3つのうち、どれがどのくらい記憶に残るかを実験しました。
5分後の平均再生数を調べると、
具体語:25回
抽象語:15回
さらに、1週間後に再実験したところ、平均再生率は
具体語:10回
抽象語:5回
という結果でした。絵が一番記憶に残りやすいことは想像に難くないですが、驚くべきは、絵と抽象語の差です。5分後の再生では2倍、1週間後の再生では4倍に近い差が出たことになります。
ちょっとわかりにくい話ですが、一言で言うと、絵などのイメージは記憶に残るということです。同時に、抽象語は残念ながら、記憶に残らない。
私たちはつい「ちゃんとしなさい」とか、「やる気を出せ」と人に言ってしまうのですが、これだと記憶に残らないのです。記憶に残すためには、できるだけ具体的に、可能なら、絵にしてイメージ化するのが有効です。
イメージ化しよう
さらにペイヴィオは、言葉だけで説明する、図や絵などのイメージだけで説明するよりも、言葉とイメージの両方を同時に見せることで、より記憶が促進されると示しました。これは二重符号化理論と呼ばれています。
説明の際、どうしても言葉だけに頼りがちですが、イメージ化して伝えられないかを検討してみてください。
ここで考えてみましょう。
あなたが思う「ちゃんと」「しっかり」とは、どんな状態でしょうか?
「ちゃんと見直しをしなさい」と言う場合、人によって基準が様々です。ひとつひとつ解き直しすることが見直しの人もいるだろうし、一目して終わりの人もいる。解きなおすことが「見直しだ」と主張する人は、一目して終わりの人に「ちゃんとしろ!」と言いそうです。でも、認識が違うから、きっと全然伝わらないでしょうね。
私の場合、「ちゃんと見直す」とは、指さし確認を意味します。
解答欄一つ一つを指でなぞり、動かしながら解答をチェックする。指を使わなかったら見直ししたと認めません。
「ちゃんと見直しして!」と言いたくなったら、指でひとつひとつなぞってみせて、「こんなふうに見直ししてみてね」と伝えます。
実物を見せたり、絵をかいたり。具体的に想像できるように伝えてあげるのがポイント!
これで、あなたの話は「ちゃんと」伝わるはず!
・・・おっと、いけない。これであなたの話は「わかりやすく」伝わるはず!
分かりやすい説明のコツ⑤ 3で語る

わかりやすい説明は3で語る
3で語る
何かを語るときは、3という数字を使うと伝わります。
「コツは3つあります」
「3ステップでできます」
というように、教えることを3つの観点に分解して説明すると、それだけでわかりやすくなります。3というのは、非常にバランスのとれた数字なのです。ここテスト出ますよ(出ません)
「要点は二つです」と言われると、2つではなんだか少ない気がするし、4つでは「なんか多い」気がします。覚えることが多すぎる。
例えば、こんなアドバイス、どうですか?

解く前にテストの全体を見直してから解くんだよ。あと見直しを忘れずにするんだよ!あなたなら絶対できるから!大丈夫!気合と根性!じゃあ!頑張って!
なんだか熱い感じがしますが・・・ちょっと情報量が多いというか・・・

…で?なんなの?
という感想を持たれてしまうかもしれません。
ですが、多くの方がこういう教え方をしてしまいます。
これを3つに分解すると、
①まずはテスト全体をみて、出来そうな問題にチェックをつけようね。
②チェックした問題を解こうね。
③見直そうね。チェックを付けなかった問題は無理してやらなくていいからね。
こんな感じで、3ステップに分けて話します。やることがはっきりして、すっきりした感じになります。
これを説明し終えてから、「チェック 解く 見直す」と相手と一緒に復唱すれば、忘れにくいです。
なぜ3つなのか?
なぜ3がいいのか?実は、これには理由があります。鼎(かなえ)ってご存知ですか?古代中国で使われた、三本足の鉄のかまのことです。
鉄の釜を立たせるためには、足が2本だとグラつきます。安定させるには、最低でも足が3本必要なのです。
このことから、3という数字は安定の数字と言われるようになりました。
三大夜景、三国志、三審制、三次元、三部作、石の上にも三年、仏の顔も三度まで。3が付く言葉はこんなにもたくさんあります。
3と言われると、教わる側は安心して聞いていられるのですね。
脳科学的にも、3というのはいい数字なのだそうです。
人間が一度に考えられるのは3つまでで、それ以上のことを覚えられません。4つだと多くて覚えられない、ふたつだと少なすぎるのです。
教えるときは、三つに分解してみてください。これだけで、聞いている人は安心感を覚え、あなたの話をじっくり聞いてくれるでしょう。
わかりやすい説明のコツ⑥ 理由を説明する

わかりやすい質問には「理由」が必要です。
多くの人がハマる落とし穴
多くの人が、何か依頼をしたり、仕事の手順を伝えるときに、「やり方」だけを伝えてしまいます。
心当たりはありませんか?
たとえば、

「この資料をA4モノクロ2in1で100部コピーして」
という情報は、やり方についての情報です。仕事を頼むなら、これだけでも問題なさそうです。
とにかくコピーを取るのが最終目的である以上、なぜそれが必要であるのかはわざわざ伝える必要がないかもしれません。時間ももったいないですし。
しかし、言われた相手は黙ってコピー機に向かいつつ、内心こう思っているでしょう。
「なんでモノクロ?」
「なんで2in1?」
「なんで100部も?」
「ってかなんで俺がやるわけ?」(これが一番大きいかもしれない)
理由なく何かをしてもらうのは、上司の権限や圧力を行使して仕事をしていることになってしまいます。相手は内心、納得しきれていないかもしれません。
例えば、こんな言い方だったら、どうでしょうか。

会社の部長が集まる会議があるから、スライド資料を2in1モノクロで100部印刷してほしい。部数が多いから、仕事が丁寧で確実で早い君に頼みたいんだよ
と言われたらどうですか?
私だったらノリノリでコピー機に行きますね…。後半の仕事が丁寧云々が嘘だとしても(笑)。
このように、伝えるときに理由を言うことで、人が動きやすくなります。
根拠のない説明は害悪だ!
そもそも論になりますが、説明とはなんでしょう?説明とは何か説明できますか?
辞書によれば、「説」という字はみちすじを表し、「明」という字は、あきらかにする、はっきり見えるようにする、という意味を示します。
「説明」とは、根拠、理由を明確にしながら、道筋を明らかにすることです。
暗いまま、前の道が見えないのでは伝わりません。道筋を照らし、道順の全体像、ポイント、分かれ道、着地点がしっかり見えるように導けるのが、良い説明といえます。
つまり、根拠、理由がないのなら、説明とはいえないのです。
「いいからやれ」は通用しない
説明の際にありがちなのは「どうやるのか」という部分だけを伝えてしまうこと。シンプル化する上では重要な観点ではあります。
しかし、人を動かすためには、「どうやるのか」の情報だけでは不十分です。
人間は、自分の行動に対して意義や根拠を求める生き物です。相手が小学生程度の子どもであれば、根拠がなくても通用するのでしょうが、相手が大人であればあるほど、何かを要求するときには根拠が求められます。
根拠はなんでもいい説
心理学の「カチッサー効果」によると、理由付けをするだけで依頼の承諾率がアップするという実験結果が出ています。
アメリカの心理学者エレン・ランガーは、コピーを取りたい時、先頭の人に先にコピーさせてもらえるよう、3通りに依頼する実験を行いました。
①「すみません、5枚なのですが、先にコピーをとらせてもらえませんか? 」と要求だけを伝える場合
②「すみません、5枚なのですが、急いでいるので先にコピーをとらせてもらえませんか? 」本当の理由を伝える
③「すみません、5枚なのですが、コピーをとらなければいけないので先にコピーをとらせてもらえませんか? 」と、もっともらしい理由を付け足す
①の場合の承諾率は60%であるのに対し、②の場合は94パーセント。③のようなもっともらしい理由付けでも93%承諾されることが証明されました。
つまり、理由があったほうが人は納得するということなのです。たとえそれがもっともらしい適当な理由だとしても。
わかりやすい説明のコツ まとめ
相手がなかなか行動してくれないとき、ついつい私たちは「いいからやってよ!」と言ってしまいます。
では人は付いてこない、納得感を持もって動けないのです。つまり、理由の内容というよりも、きちんと「理由がある」ことの方が重要なのです。
人を動かす際には、どうやるか、何をやるかだけでなく、なぜやるかも忘れずに付け足してみてください。
ところで、「ちゃんと」「しっかり」という言葉って、とても便利ですよね。説明の際についつい使ってしまいませんか?
この言葉って、相手に全然伝わらないんですよね。自分が思う「ちゃんと」「しっかり」が相手と同じとは限らない。私は何度もこの言葉を使って失敗しました(笑)。
とはいえ、この言葉はついつい無意識的に使ってしまうこともあるものでしょう。
そこで、なぜ説明で「ちゃんと」「しっかり」を使うべきではないのか、代わりにどんな表現を使えばいいのかを考えたいと思います。
どんなときでもバッチリ伝わるコツ
どんなときでもバッチリ伝えたい方はこちらをご覧ください!
心理学に基づいた伝わる法則が55個掲載されています。あなたの説明力が向上すること間違いなしですよ~!!
以上、横浜プロ家庭教師佐々木(@kateikyo_megumi)でした!


▼ 教えてもやってくれない、覚えてくれない人の頭の中はどうなっているのか










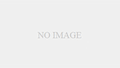
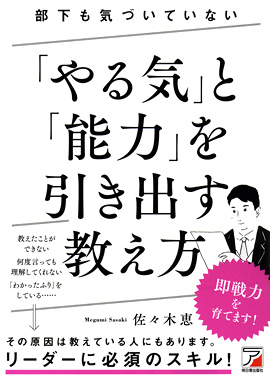


カテゴリー