こんにちは。横浜・鎌倉のプロ家庭教師 佐々木(@kateikyo_megumi)です。
昨日の記事にたくさんの反響をいただきました。昨日の記事→人を変えたいと思っている人は何も変えられない
私は「人を変えることもできないし、人を動かすこともできない」という前提に立っています。あくまで決定権は相手にあることを念頭に置きながら、なぜ勉強が必要か、どうして勉強してほしいのかを伝えます。決めるのは相手。
私は相手に代わることはできないから、相手の人に動いてもらえるように働きかけることしかできないのです。
ですが、相手を動かすことができる言葉が、たった一つだけある。と私は思います。
もちろん、その方法を使えば必ず相手が動いてくれるというわけではありません。
ですが、強制力や抑止力を持って人を動かそうとするよりも、効果はあるでしょう。
どんな言葉だと思いますか?
強制と制限は反発を生む
勉強しなさい、ゲームするな、では人は反発します。心理的リアクタンスの働きで、強制されたり、制限されると反対に向かいたくなるもの。
心理的リアクタンスについてはこちらに詳しく書きました。
私だってそうです。強制されたらやりたくありませんし、制限されたら反発します。
そこにはたいてい、上下関係が存在します。相手を管理したい、思い通りに動かしたいと思えば思うほど抵抗されてしまうでしょう。
管理の関係は、親と子どもの関係です。管理する側が上で、される側が下。下に回された人間は、どんな感情を抱くでしょうか?
心理学者トマス・ハリス博士によると、コミュニケーションには親、子、大人の3つの役割が存在するそうです。相手や状況によって、その特徴のどれかを示そうとします。
親は、相手を非難し、管理しようとします。親の役割をする人は、上から目線で「子」を厳しく律しようとします。
子は、自分を被害者とみなします。上から管理しようとする大人に反発心を抱きます。
大人は、誰とでも上手くコミュニケーションをとり、相手を対等に扱い、相手に敬意を持って接します。
コミュニケーションがうまくいかないのは、自分と相手を親と子の関係に持ち込んでしまっているせいです。
他人を動かしたい、他人を変えたいと考えている人は、無意識のうちに親を演じてしまっているのでしょう。子ども扱いされた相手は反発するか、離れていきます。
コミュニケーションの原則は対等
実の親子でさえ、親と子の関係に持ち込んでは失敗します。では、どういった関係が理想なのでしょうか?
その上で知っておくべきことは、コミュニケーションは対等であるべきという考え方。
つまり、両方が大人であるということです。互いが互いを尊敬しあうこと、つまり「人は変えられない」「決めるのはその人自身」ということを受け入れた状態です。
言い換えれば、友達に接するような態度です。
思春期頃から親や先生の言うことは聞かなくなるけれど、友達の話にはきちんと耳を傾けていたはず。それは、友達の言葉は対等だから。圧力がないからです。
相手をやる気にする言葉とは?
前置きが長くなりましたが、相手を動かすためには上下関係を作らないこと、対等な関係でいるということが重要です。友人のように接するとも言えるでしょう。
「勉強しなさい」は完全に、相手を変えようとする親の言葉。
対等な言葉とは、何か。もし相手が友達なら、あなたはなんと言いますか?友達に何かをしてほしい時、なんと言えばいいでしょうか。
人を動かせる言葉がたったひとつだけあるなら、「一緒にやろう」だと私は考えます。
前から引っ張るのでもなく、後ろから押すのでもなく、ともに歩こう、走ろうという姿勢。相手を動かしてやろう、変えてやろうではなく、ともに動き、変わろうとする姿勢です。
相手に強制するのではなく、自分も動こうとする姿勢。こんなふうに声を掛けて、一緒に歩こうとしてくれる人がいたら、どうでしょうか。きっと、心強いはずです。
もし、あなたが何か始めたくて、でも躊躇しているときにこの言葉を言われたら、踏み出してみようと思いませんか。
押すのではなく、一緒に横を走る。相手が少し前に出たら、追いつくために、一歩踏み出して見たいと思うのではないでしょうか。相手との信頼関係があるのなら、なおさら。
その姿勢と、実際の行動を見た時、相手は真剣に考えることでしょう。
ただし、それでも最終決定は相手のものであることを忘れてはいけません。
いつだって対等に。一方的に動かすのではなく、ともに動く。
そんな姿勢で、人と関わっていきたいものです。
教え方の本を出しました!
人にやる気を出してほしい、積極的に動いてもらえる教え方を身につけたい人はぜひご一読ください!






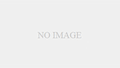
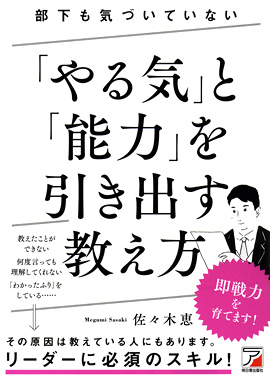


カテゴリー