こんにちは。横浜・鎌倉のプロ家庭教師 佐々木(@kateikyo_megumi)です。
先日、整理収納アドバイザー2級の講座を受講しました!
最近人気の資格「整理収納アドバイザー」。流行に乗っかって、資格口座を受講してきましたよ~!
整理収納アドバイザー2級の認定証が届きました。
散らかった机や子ども部屋のお片づけを通じて、さらなる成績アップをサポートしていきたいと思います✨
1級目指して勉強するぞー pic.twitter.com/iTXiqdrXJv
— ささき めぐみ@横浜鎌倉プロ家庭教師 (@kateikyo_megumi) October 20, 2018
2級の認定証をゲット!どうしてカタカナなの…?(´・ω・`)
で、私は一応勉強の専門家なので、どんな講座だったか、試験はどうだったかを全部書いてしまいたいと思います!
・整理収納アドバイザー2級の講座ってどんなことを学ぶの?
・テストあるらしいけど難易度は?
・ぶっちゃけこの資格役に立つの?
などなど書いちゃいたいと思います!
整理収納アドバイザーとは?
整理収納アドバイザー資格とは、ハウスキーピング協会が講座を主催し、資格認定している試験です。
「探し物がなかなか見つからない」「片づけてもすぐにリバウンドしてしまう」こんなことで悩んだご経験はありませんか?
当協会では、物や部屋が片付かない原因を根本的に解決するためのノウハウ ・メソッドをお伝えするための資格講座をご用意しています。
(ハウスキーピング協会サイト 「整理収納アドバイザーとは」 より
整理収納、つまり片付けに関する民間資格ということですね!
概要
- 受講料 23,100円(税込)※テキスト・認定料込
- 受講時間 10:00~17:00
- 受験資格 日本語が理解できる方
- 資格有効期限 なし。更新の必要なし。
- 申込み方法 ハウスキーピング協会サイトから申し込み
講座開講スケジュールを見ると、毎週のようにどこかで開催されていますので、好きなタイミングで受講ができそうです。
2級は個人の能力向上が目的で、プロとして仕事にするのであれば1級取得が求められます。
詳細はこちらをご覧ください。

整理収納アドバイザー2級 知ったきっかけ
なぜ急に、勉強とは関係なさそうに見える「整理収納」の資格を取りに行ったかというと、
家の収納に悩んで
引っ越しを機に、家の収納について考えざるを得なくなりました。引っ越しの荷物をまとめてみたら、
「うわ…私の荷物、多すぎ?」
そこで仕方なく片付けを始めたわけですが、せっかくなら本でも読んで学んでみようと思って本屋言ったものの、
ときめくとは何やねん!!?( ゚д゚)
私は理屈っぽいところがあるので、感覚的なこととか体験ベースの本では納得しできないんですよ…面倒くさいですね。
そんな折に、こんな本に出会ったんです。
この本をパラパラ読んでみたのですが、マンガ形式でわかりやすく、しかも理論的に、整理収納の方法を学ぶことが出来ました。
著者の長浜のり子先生のプロフィールに、「整理収納アドバイザー1級」と書かれています。
他にも片付け絡みの本を何冊か読んでみたのですが、どの本も著者の先生に「整理収納アドバイザー」と書かれています。
なんなんだこの資格は!
というわけで興味を持ち、調べたら面白そうなので、ノリで受けてみようかなと。
仕事に役立ちそう
私は家庭教師なので、当たり前ですがたくさんの家にお邪魔します。
そうすると、けっこういるんですよね、片付けできない生徒さん。
つねに教科書やらプリントが散乱していて、「あれってどこにある?」と聞いてもすぐに出てこない。教材探しに時間がとられてしまいます。
試験前に、生徒さんのプリント整理を手伝ったこともありまして、その時に思ったんですよね。
「整理収納の方法をきちんと学んでアドバイスできたら、もっと生徒さんの成績を上げられるかも…!
気づいちゃったんです。これは面白いかもしれない。
しかも客間だけでなくリビングやら子ども部屋まで上がることができるのはこの仕事特有かもしれません。
つまり、お客様のご家庭を隅々まで見れてしまうので、子ども部屋だけでなく、おうちの整理収納に困っているお客様のお役に立てるかも!?と考えたわけです。
整理収納アドバイザー2級 受講内容
講座全体は10:30~17:30の7時間でした。
途中、お昼休憩が1時間あり、最後30分は認定試験なので、講座を受けるのは実質5時間半です(時間は会場によって違うようなので確認が必要です)。
午前:理論
午後:理論と実習、そのあと試験
こんな感じのタイムスケジュールでした。
整理収納アドバイザー2級 内容チラ見せ
整理とは?
まず、「整理とは何か」についての話があります。
整理とは、必要、不必要なものを仕分けていくこと。不必要なものが多いままで収納を極めても、不必要なモノをしまいこんでしまうだけかもしれない。
この「整理」が一番重要で、一番大変で、一番難しいのです。
どうやって整理すればいいの?
モノを4つにカテゴライズしていきます。
- アクティブ 毎日使うようなモノ
- スタンバイ 普段使いではないが時々使うモノ。季節外の洋服や季節家電など
- プロパティ 所有しているだけのもの
- スクラップ 廃棄を待つ
整理する場所のモノを全て出して、この4領域に分類していきます。
スクラップはもちろん即捨て。収納ではスタンバイを奥に、アクティブを使いやすい場所におくのがポイントです。難しいのはプロパティ(所有)の取り扱い。ここに入っているものをどう処理するのかがポイントになります。
収納のポイントは?
「整理収納5つの鉄則」にのっとって収納していきます。
①適正量の決定
収納しきれないとしたら、それは適正量をオーバーしているのかも
②動作・動線にかなった収納
家事動線は3つあります。調理動線、掃除動線、洗濯動線。それぞれ動線が短ければ短いほど効率的。ちなみに、一般的に一番動線が長いのが洗濯動線。
③使用頻度別収納
よく使うモノは手前、たまに使うモノは奥へ。
場所としては中(目の高さから腰の高さあたり)→下→上の順番で使いやすいので、使用頻度が高いモノは中へ。それほどでもないモノは下へ。滅多に使わないモノは上へ。上に収納するときは重いものは置かないようにし、取っ手をつけて取りやすく。
④グルーピングの効果
モノの分け方にも一工夫を。
洋服は人別に分けるのは当然ですね。
例えば、冠婚葬祭に使うバッグや祝儀袋、ふくさ、筆ペンなどは1つにまとめておくと何かあったときに焦らずにすみます。筆ペンってこういう時に使うことがほとんどなので、ペン入れではなく冠婚葬祭グループにしておいた方が探さなくて良さそう。
⑤定位置管理
そうしてモノの定位置を決めたら、とりあえず崩さずにその定位置を守ります。
片付けが苦手な人は、モノの定位置管理ができてない…とはよく聞きますね。
定位置管理ができないのは、収納の仕方が使用頻度別になっていない、使いやすいグルーピングがされていないなど、効率面の問題もあるかもしれません。まずは、これらの鉄則に基づいて定位置を決めて収納することが大事ですね。
ただ、生きていれば考えが変わることも、ライフスタイルが変わることもあるので、より良い使い方を発見したら、定位置の変更は柔軟にしてOK。
実習
散らかったクローゼットの写真と、依頼者の要望を見ながら、適切な整理収納をアドバイスする実習があります。こちらはグループワーク。
グループごとに、整理収納方法をまとめて模造紙に書き、発表。
これで講座は終了です。
整理収納アドバイザー2級 テキスト
公式テキストとして、こちらの本「一番わかりやすい整理入門」をいただきました。
この本、Amazonでも購入できます。
受けてみようか迷っている方は、一度読んでみるといいかもしれません。
整理収納アドバイザー2級 認定試験
講座の後に認定試験がありました。
ただ、この試験は「合格率100%なのでご安心を」と先生がおっしゃっていました(笑)。
問題も、A41枚、○×問題が15題程度。しかもテキストを見てOK。その日まじめに講座を受けていて、よほどのことがなければ合格できます。
「テストなんてもうウン十年受けてないわ!」という方でも安心して受講しましょう。
受講中に「ここは大事ですよ」と先生に言われたところにふせんをつけておくと良いですね!
整理収納アドバイザー2級 受けてみて感想
「片付けができないのは、だらしがないから」と一言で片付けられがちですが、そうではなさそうです。
Aさんの整理収納は、Bさんにとっては使いにくいかもしれない。
人それぞれ、モノとの付き合い方は違います。Aさんは毎日使うボールペンを、Bさんは月一しか使わないかもしれません。それなら、収納の仕方が変わるのもとうぜんです。その人に合った片付け方があるのです。
これはこうしましょうと決めてしまうのではなく、大原則を教えて、各人が考えて整理収納することが大切だと学びました。
今後の目標
整理収納アドバイザー1級取得を目指します。
今回は軽い気持ちで2級を受講しましたが、せっかく勉強したし、仕事にもうまく活かせそうなので、やるならきちんと最後まで勉強しておきたいと思います。
さらに、学習机の整理収納アドバイスができるように勉強していく予定です。
もちろん、このブログにも整理収納のコツを書いていきます!
学習机が散らかっているせいで、勉強時間を無駄にしてしまったり、勉強のやる気を削いでいたり、親御さんとケンカしてしまう生徒さんが少なくないのです。
学習机のストレスが減れば、勉強のやる気も上がるのでは…と楽しみにしています。
また1級を受験したらレポートします。
以上、横浜プロ家庭教師佐々木でした!
追記!
1級1次試験(筆記試験)合格できました。試験で出題された内容や、勉強法をまとめています。





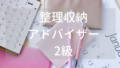



カテゴリー