「将来の夢は何?」
学生なら必ず、作文ネタとして定期的に取り上げられるテーマですね。大人になってからは、急に疎遠になるお話でもありますね。
「将来の夢のために勉強する」というモチベーションで勉強を頑張る人もいるので、「夢ってなに?」「将来の夢って何?」というのは私にとって常に気になるテーマであります。
そこで、この本を読んでみました。
この本は、工業博士であり作家でもある森博嗣先生が、どのようにしてその夢を叶えてきたかが書かれている本です。
私はあまり小説を読まないので、森博嗣先生を知っていたわけではなく、この本のタイトルに純粋に惹かれてこの本を手に取りました。
そんなわけで、森博嗣先生の生い立ちや作品を知っているわけではないニワカですが…(笑)。それでもこの本は大変おもしろかったです。森先生の小説を読んでみたくなりました。
森博嗣先生は、小さい頃に雑誌で見た鉄道模型に惹かれ、自分もそんな鉄道を作って遊びたい!という夢を描いたそうです。その夢を実現するにはどうすればいいか、特に鉄道模型には相当な資金が必要ですから、資金面をどうするかを考えたそう。
そこで、大学の助教授で文章を書けるから、儲かりそうだからと小説を書いたら大当たりした…という。
正直、めちゃくちゃ羨ましいです(笑)。
夢とは何か?
森博嗣先生は、もともと大学教授を夢見たわけでも、作家を夢見たわけでもなかったそうです。
夢は自宅に鉄道模型をつくること。大学教授も、作家も、その手段でしかなかったのでした。
夢とは一体何なのでしょう?
本書では、夢とは自分の自由の追求であると書かれています。自分がやりたいと思えることをする。森先生にとって職業はその手段にすぎないのですね。
例えば、結婚式を盛大に挙げたいとか、カッコイイ人と結婚したいという夢はどうでしょうか?
それを誰かに見せたい、見せて自慢するための夢になっているとすれば、これは「見せたい夢」であり、ほんとうの意味での「自分の夢」ではないのです。
同時に、多くの人が、他者の目を気にしすぎていると警鐘を鳴らしています。自分が見たい夢ではなく、見せたい夢に走ってしまっている、と。
せっかくの人生、自分のための人生。知らず知らずのうちに誰かの夢をかなえるために毎日自分を使っているとしたら、なんともったいない。
自分の自由の追求。それこそが自分の夢。他人の評価を排除した夢は強い夢になるのです。
夢=職業のジレンマ
学生に「夢は何?」と聞くと、「お医者さんになりたい」「ケーキ屋さんになりたい」と、大半の人は職業名を答えます。
私はここに違和感を感じています。
その夢を実現したら人生が終わってしまう気がして。晴れて「夢であった」職業に就けたとして、その後どうするのだろうと。就職がゴールではないはずです。
加えて、社会を知らない子どもが、職業という枠組みだけで将来を決めてしまっていいのかという危惧もあります。
子どもが知っている職業って、学校教師、お医者さん、両親の職業、プラスアルファ程度ではないかと思うのです。お店の店員とか、それくらいしか選択肢がない中で、「将来の夢を持とう(なりたい職業を決めよう)」と促すことにすごく違和感を感じるのですね。
将来の夢がない子どもたち
生徒さんから「将来の夢がありません」と相談されるのですが、話をよく聞いてみると、将来の夢がないのではなく、なりたい職業が決まっていないのです。
その時は、こう質問します。
「こんな風になりたい!こんな風に生きていけたら幸せ!みたいなイメージはある?」
というと、返答はだいたいこれ。
「お金持ちになりたいです」
お金持ち。誰もが夢見ることですね。でも、多くの人はお金そのもの、紙幣そのものが好きとか、諭吉先生を敬愛しているわけではありません。お金そのものに興味があるわけではなく、お金を使って何かを得たいと思っています。当たり前ですが。
そこで、さらに質問します。
「お金持ちになって、何をしたいの?」
そうすると、その人の価値観が透けて見えるのです。
「都会に住みたい」「田舎に住みたい」「サッカーを毎日観戦したい」「○○の服を来て街を歩きたい」「子どもに囲まれて暮らしたい」「コレクションを飾れる家が欲しい」「夜景を見ながらカクテル転がしたい」「外車がほしい」などなど。
これが、森博嗣先生の言う、その人自身が見たい夢ではないかと思います。
夢と目標の違い
職業名や、進学したい学校名を夢にするのもいいけれど、少なからず他人の評価を気にしている面があって、見せたい夢になっている気がします。
私は思います。
夢ってもっと壮大で、非現実的で、自分勝手で、「そんなの無理でしょ~!」人から笑われるようなものでいいのではないかと。
職業は、夢をかなえるための手段であり、「そんなの無理!」と思える場所に行くためのそ通過点。
言い換えると、職業とはたんなる目標。つまり、職業はすごく現実的な視点ではないでしょうか。
夢はもっと、非現実的で、自分勝手で、ワクワクするような楽しいことでいいのではないかと思うのです。
夢を実現するためにどうすればいいんだろう?そのためにはこれくらいのお金と時間が必要だから、こういう職業についたらいいかもね、というのが私の考える理想です。
そういう私は?
この話をすると絶対に聞かれるので私の話も。
子どもの頃の夢が「家庭教師」だったわけではありません。それより、人のためになることがしたかったんです。人の記憶に強く残る仕事がしたかったのです。
よく、「人は二度死ぬ」といいますよね。一度目は肉体の死。生物的な死です。二度目は記憶の死。私のことを知っていた人たちから、私の記憶が消えていくのが二度目の死。
私は昔から体が弱いほうで、肉体の長生きは望めないだろうなと。それならもう一方で長生きしたい。だから、誰かの人生を良い方に変えられるような、そんな生き方がしたい。
体が弱い分、頭を意識的に鍛えてきました。できるだけ知恵と知識で勝負したい。朝は寝ていたい。読書する時間がたっぷりほしい。縛られず自由な生き方がしたい。
家庭教師の仕事は夜がメインなので、朝はゆったりできますし、訪問まではブログを書いたり読書したり。自分の願望すべてを叶えられる現在のライフスタイル、最高です。
もっとみんな、夢を見よう
それなのに子どもたちが職業とか現実的なことしか言えないのは、大人の責任です。大人がそういう風に子どもを縛っているからですよね。
でもそれも仕方がないと思うのです。
大人だって、社会の中で必死に生きているわけですし。現実的な思考になり、現実面で子どもを心配するのは至極まっとうな話で。
だからこそ。「大人も夢を見よう」と言いたいし、きっと森先生もそう伝えるのが趣旨だったのではないかと思うのです。
大人が夢を見て、楽しく生きていたら、子どもたちも真似して、夢をもって楽しく生きようとするでしょう。
そんな連鎖が出来たらすごく幸せですよね。
まずはみんなで夢を見ましょう♪



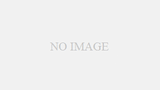

カテゴリー