こんにちは。横浜・鎌倉のプロ家庭教師 佐々木(@kateikyo_megumi)です。
・できるだけ苦労せずに勉強ができるようになりたい
・勉強して自分の目標を達成したい
そんな気持ちを誰でも持っていると思います。
当記事では、実際に400人以上の生徒に教えて成果を出してきた勉強法や、苦手克服の方法を書いています。
これを実践すれば勉強のコツがわかり、成績が上がるはず。
ぜひ一緒に取り組みましょう!
勉強のヒント
最初に読んでもらいたい記事をまとめました。
・ 簡単にできる勉強法15選 自分に合った勉強法を見つけよう!
苦手科目の勉強法
苦手科目・苦手教科とどう付き合えばいいのか?苦手克服専門の家庭教師が、苦手との向き合い方、克服法をまとめました。
授業の受け方
学校などで授業を受けるときに「わからない」とツライですよね。授業わかるようになる方法をまとめました。
・ 成績が上がる!先生に褒められる(かもしれない)ノートの取り方・選び方
勉強を続ける方法
勉強が続かない方、なぜかいつも3日坊主になる方はこちらもどうぞ。
・ 勉強が続かない人におすすめしたい 勉強を毎日続ける方法【継続は力なり】
テスト対策
どんなに勉強を頑張っても、テストの点が上がらないと評価されません。そこで、テスト勉強のやり方やコツをまとめた記事です。
・ 新学年最初の試験に向けて!ゴールデンウイークにやっておきたいテスト対策
・ 勉強しているのに!?点数が上がらない人が陥っている4つの落とし穴と対策法
伸び悩みの時の勉強法
勉強していて、伸びなくなったときにどうすればいいかをまとめました。
・ 勉強しても成果が出ないのは「なんのため」を考えていないから
・ 勉強しているのに成果が出ない人に知ってほしい「学びのステップ」の話
時間帯別の勉強法
脳は時間によって得意なことが違います。それぞれの時間に合った勉強法を実践すれば楽に成果を出せるかも。
・ 時間帯別の勉強法 朝は思考、夜は暗記?時間を上手に使って勉強する方法
科目別勉強法
各教科別の勉強法をまとめています。
英語
社会
・ これでわかる!歴史の勉強法(中学校の歴史・高校の日本史、世界史対策)
数学
・ 数学の苦手を克服する勉強法 数学苦手がクラス1位をとった勉強法とは
国語
・ 国語の勉強法 国語はセンスではない!国語にも勉強法がある
・ 国語の苦手は2タイプ!国語の点を上げる勉強法 (中学生・高校受験生向け)
・ 中学生の論文・作文の構成法 「こんなに書けない!」を解消する方法
理科
暗記のやり方
暗記については別のカテゴリーに記事を載せています。









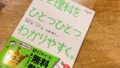
コメント